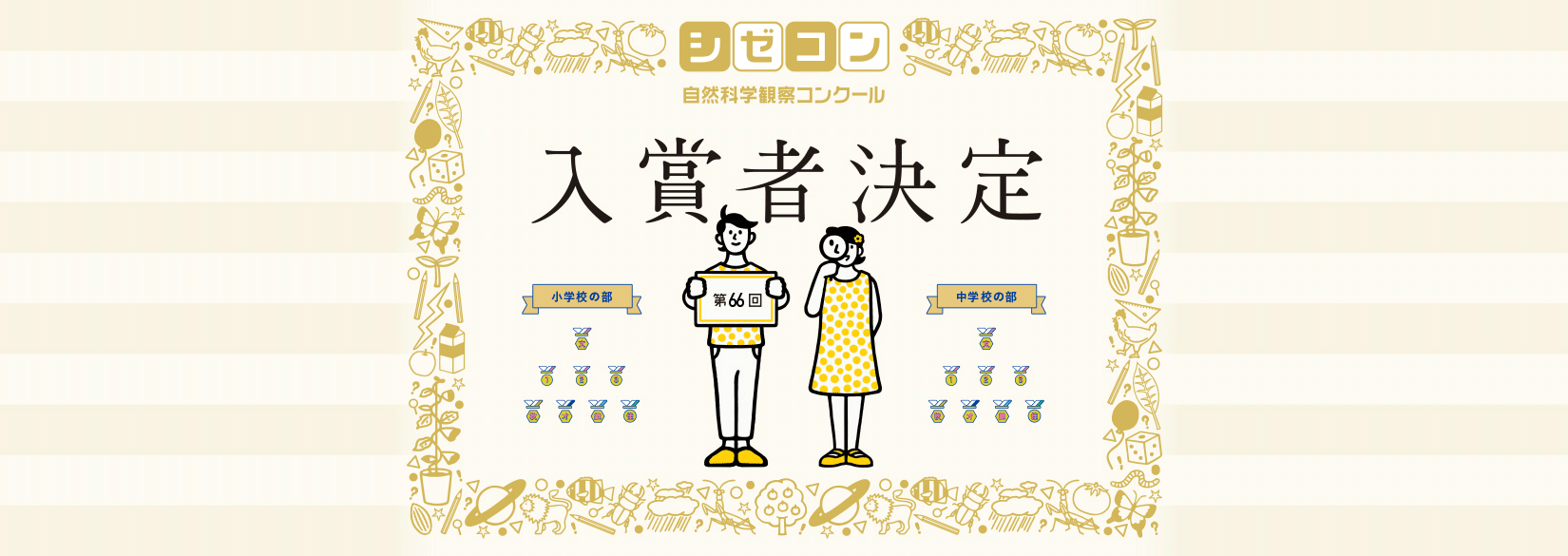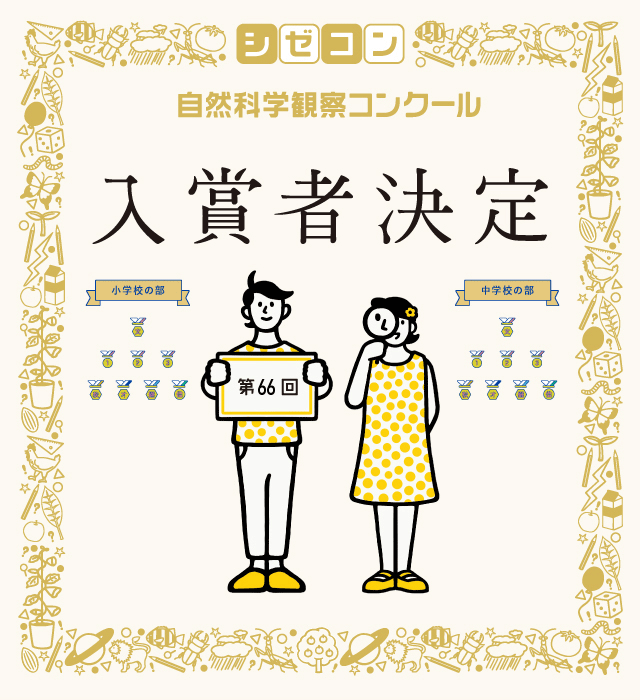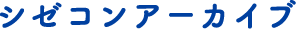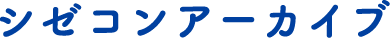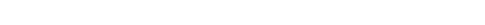小学校の部
-
 文部科学大臣賞エサ条件によるプラナリアの成長と自切に及ぼす影響東京都荒川区立第四峡田小学校 4年佐藤 大悟さん
文部科学大臣賞エサ条件によるプラナリアの成長と自切に及ぼす影響東京都荒川区立第四峡田小学校 4年佐藤 大悟さん -
 1等賞柿崎漁港の海岸の貝の研究 Part2 ~海水温上昇との関係~新潟県上越市立春日新田小学校 5年樋口 葵人さん
1等賞柿崎漁港の海岸の貝の研究 Part2 ~海水温上昇との関係~新潟県上越市立春日新田小学校 5年樋口 葵人さん -
 2等賞テントウムシの研究 パート3 ~自然界でのサバイバル能力~茨城県つくば市立吾妻小学校 5年川瀬 美羽さん
2等賞テントウムシの研究 パート3 ~自然界でのサバイバル能力~茨城県つくば市立吾妻小学校 5年川瀬 美羽さん -
 3等賞カブトムシの観察 パート5 ~カブトムシの飛翔力を明らかにする~富山県高岡市立牧野小学校 5年田中 晴斗さん
3等賞カブトムシの観察 パート5 ~カブトムシの飛翔力を明らかにする~富山県高岡市立牧野小学校 5年田中 晴斗さん -
 秋山仁特別賞スーっと動く味そ汁のひみつ Part2 ~断続的な動きの理由&面にまく液体の条件~石川県金沢市立大徳小学校 4年田嶋 花帆さん
秋山仁特別賞スーっと動く味そ汁のひみつ Part2 ~断続的な動きの理由&面にまく液体の条件~石川県金沢市立大徳小学校 4年田嶋 花帆さん -
 オリンパス特別賞暑い夏を乗り切ろう!体のクールダウン大作戦! part2富山県富山大学教育学部附属小学校 4年中山 桃嘉さん
オリンパス特別賞暑い夏を乗り切ろう!体のクールダウン大作戦! part2富山県富山大学教育学部附属小学校 4年中山 桃嘉さん -
 継続研究奨励賞世界に広まれ、「しがきん」の発こう力! ~乳酸きんの救出と長期保存に成功~京都府同志社小学校 6年清水 結香さん
継続研究奨励賞世界に広まれ、「しがきん」の発こう力! ~乳酸きんの救出と長期保存に成功~京都府同志社小学校 6年清水 結香さん -
 佳作いろいろな液体によるウミホタルの光り方研究山形県酒田市立八幡小学校 6年信夫 遥一郎さん
佳作いろいろな液体によるウミホタルの光り方研究山形県酒田市立八幡小学校 6年信夫 遥一郎さん -
 佳作干からびた田んぼによみがえるいのち ~ミジンコの小さなきせき~千葉県柏市立十余二小学校 2年藤本 健太さん
佳作干からびた田んぼによみがえるいのち ~ミジンコの小さなきせき~千葉県柏市立十余二小学校 2年藤本 健太さん -
 佳作9種類の虫の脚を比べる!ガラスをのぼれる虫とのぼれない虫の脚の違いは何だろう?兵庫県神戸市立美野丘小学校 3年鈴木 宜親さん
佳作9種類の虫の脚を比べる!ガラスをのぼれる虫とのぼれない虫の脚の違いは何だろう?兵庫県神戸市立美野丘小学校 3年鈴木 宜親さん -
 佳作薬が飲みやすくなるコップ形状の研究とその効果の実証実験広島県AIC国際学院 広島初等部 4年広沢 嵩政さん
佳作薬が飲みやすくなるコップ形状の研究とその効果の実証実験広島県AIC国際学院 広島初等部 4年広沢 嵩政さん -
 佳作びっくり!カブトエビ② ~乾燥卵の目覚まし大作戦!~滋賀県大津市立中央小学校 3年中嶌 紘花さん
佳作びっくり!カブトエビ② ~乾燥卵の目覚まし大作戦!~滋賀県大津市立中央小学校 3年中嶌 紘花さん -
 佳作泳ぐとできる波について京都府京都市立京極小学校 6年吉﨑 十杏さん
佳作泳ぐとできる波について京都府京都市立京極小学校 6年吉﨑 十杏さん -
 佳作地球にやさしいエネルギーを作りたい! PARTⅢ ~太陽エネルギーで動かす!発電から充電に挑戦する~静岡県浜松市立中郡小学校 6年袴田 知生さん
佳作地球にやさしいエネルギーを作りたい! PARTⅢ ~太陽エネルギーで動かす!発電から充電に挑戦する~静岡県浜松市立中郡小学校 6年袴田 知生さん -
 佳作ナミアゲハの春型を作れるか? Ver.5静岡県藤枝市立葉梨西北小学校 6年小長谷 咲月さん
佳作ナミアゲハの春型を作れるか? Ver.5静岡県藤枝市立葉梨西北小学校 6年小長谷 咲月さん -
 佳作セスジスズメは、お話ししているか?友だちの声をたよりに迷路を突き進め!富山県富山大学教育学部附属小学校 4年笹山 颯仁さん
佳作セスジスズメは、お話ししているか?友だちの声をたよりに迷路を突き進め!富山県富山大学教育学部附属小学校 4年笹山 颯仁さん -
 佳作アリですりこみがおきる条件とは茨城県東海村立中丸小学校 4年尾形 凪音さん
佳作アリですりこみがおきる条件とは茨城県東海村立中丸小学校 4年尾形 凪音さん -
 学校奨励賞茨城県つくば市立吾妻小学校
学校奨励賞茨城県つくば市立吾妻小学校 -
 指導奨励賞富山県富山大学教育学部附属小学校山崎 裕文先生・保井 海太朗先生
指導奨励賞富山県富山大学教育学部附属小学校山崎 裕文先生・保井 海太朗先生 -
 指導奨励賞静岡県静岡STEAMフューチャースクール増田 俊彦先生
指導奨励賞静岡県静岡STEAMフューチャースクール増田 俊彦先生 -
 指導奨励賞石川県(大学院生)藥師 功哉さん
指導奨励賞石川県(大学院生)藥師 功哉さん
文部科学大臣賞
エサ条件によるプラナリアの成長と自切に及ぼす影響
東京都荒川区立第四峡田小学校 4年
佐藤 大悟さん
1等賞
柿崎漁港の海岸の貝の研究 Part2 ~海水温上昇との関係~
新潟県上越市立春日新田小学校 5年
樋口 葵人さん
2等賞
テントウムシの研究 パート3 ~自然界でのサバイバル能力~
茨城県つくば市立吾妻小学校 5年
川瀬 美羽さん
3等賞
カブトムシの観察 パート5 ~カブトムシの飛翔力を明らかにする~
富山県高岡市立牧野小学校 5年
田中 晴斗さん
秋山仁特別賞
スーっと動く味そ汁のひみつ Part2 ~断続的な動きの理由&面にまく液体の条件~
石川県金沢市立大徳小学校 4年
田嶋 花帆さん
オリンパス特別賞
暑い夏を乗り切ろう!体のクールダウン大作戦! part2
富山県富山大学教育学部附属小学校 4年
中山 桃嘉さん
継続研究奨励賞
世界に広まれ、「しがきん」の発こう力! ~乳酸きんの救出と長期保存に成功~
京都府同志社小学校 6年
清水 結香さん
佳作
いろいろな液体によるウミホタルの光り方研究
山形県酒田市立八幡小学校 6年
信夫 遥一郎さん
佳作
干からびた田んぼによみがえるいのち ~ミジンコの小さなきせき~
千葉県柏市立十余二小学校 2年
藤本 健太さん
佳作
9種類の虫の脚を比べる!ガラスをのぼれる虫とのぼれない虫の脚の違いは何だろう?
兵庫県神戸市立美野丘小学校 3年
鈴木 宜親さん
佳作
薬が飲みやすくなるコップ形状の研究とその効果の実証実験
広島県AIC国際学院 広島初等部 4年
広沢 嵩政さん
佳作
びっくり!カブトエビ② ~乾燥卵の目覚まし大作戦!~
滋賀県大津市立中央小学校 3年
中嶌 紘花さん
佳作
泳ぐとできる波について
京都府京都市立京極小学校 6年
吉﨑 十杏さん
佳作
地球にやさしいエネルギーを作りたい! PARTⅢ ~太陽エネルギーで動かす!発電から充電に挑戦する~
静岡県浜松市立中郡小学校 6年
袴田 知生さん
佳作
ナミアゲハの春型を作れるか? Ver.5
静岡県藤枝市立葉梨西北小学校 6年
小長谷 咲月さん
佳作
セスジスズメは、お話ししているか?友だちの声をたよりに迷路を突き進め!
富山県富山大学教育学部附属小学校 4年
笹山 颯仁さん
佳作
アリですりこみがおきる条件とは
茨城県東海村立中丸小学校 4年
尾形 凪音さん
学校奨励賞
茨城県つくば市立吾妻小学校
指導奨励賞
富山県富山大学教育学部附属小学校
山崎 裕文先生・保井 海太朗先生
指導奨励賞
静岡県静岡STEAMフューチャースクール
増田 俊彦先生
指導奨励賞
石川県(大学院生)
藥師 功哉さん
中学校の部
-
 文部科学大臣賞恐竜の足跡の研究 ~僕の9年間の研究成果総括編~静岡県藤枝市立高洲中学校 3年小崎 惇さん
文部科学大臣賞恐竜の足跡の研究 ~僕の9年間の研究成果総括編~静岡県藤枝市立高洲中学校 3年小崎 惇さん -
 1等賞マッチョ・シルク ~プロテインで育てたカイコ~東京都東京学芸大学附属竹早中学校 3年土屋 光伸さん
1等賞マッチョ・シルク ~プロテインで育てたカイコ~東京都東京学芸大学附属竹早中学校 3年土屋 光伸さん -
 2等賞分光色差計を使ったAGEスケールの開発 ~誰でも簡単にできる糖化反応の評価方法~大分県立大分豊府中学校 2年宮﨑 香帆さん
2等賞分光色差計を使ったAGEスケールの開発 ~誰でも簡単にできる糖化反応の評価方法~大分県立大分豊府中学校 2年宮﨑 香帆さん -
 3等賞アゲハ蝶類の蛹化成長曲線と開翅長との関連について静岡県焼津市立大村中学校 1年青木 聡さん
3等賞アゲハ蝶類の蛹化成長曲線と開翅長との関連について静岡県焼津市立大村中学校 1年青木 聡さん -
 秋山仁特別賞アリの嗅覚能力と孤立アリが抱えるストレスについて アリの研究パートⅢ福井県福井大学教育学部附属義務教育学校 9年八木 詩月さん
秋山仁特別賞アリの嗅覚能力と孤立アリが抱えるストレスについて アリの研究パートⅢ福井県福井大学教育学部附属義務教育学校 9年八木 詩月さん -
 オリンパス特別賞両利きになることを支援する装置の開発3静岡県静岡大学教育学部附属静岡中学校 2年辻󠄀 知里さん
オリンパス特別賞両利きになることを支援する装置の開発3静岡県静岡大学教育学部附属静岡中学校 2年辻󠄀 知里さん -
 継続研究奨励賞遠州、東三河地域における二ホンアカガエルとヤマアカガエルの繁殖条件とすみ分け静岡県浜松市立可美中学校 3年伊藤 壮太さん
継続研究奨励賞遠州、東三河地域における二ホンアカガエルとヤマアカガエルの繁殖条件とすみ分け静岡県浜松市立可美中学校 3年伊藤 壮太さん -
 佳作えっ?何で漏れないの!?愛知県西尾市立鶴城中学校 タンクブロメリア班 3年・1年グェン カンアンさん・山根 悠嗣さん・小林 蒼空さん・馬場 陽大さん・レ ファイ バオさん・馬場 崇帆さん
佳作えっ?何で漏れないの!?愛知県西尾市立鶴城中学校 タンクブロメリア班 3年・1年グェン カンアンさん・山根 悠嗣さん・小林 蒼空さん・馬場 陽大さん・レ ファイ バオさん・馬場 崇帆さん -
 佳作バイオエタノール製造の最適条件の探究 ~廃棄野菜のアップサイクルを目指して~千葉県千葉市立都賀中学校 科学技術部 3年山本 佳音さん・加藤 咲菜さん・地引 明良さん・大谷 颯さん・野口 陽菜さん・中田 光さん・湯浅 那央さん・横田 大智さん
佳作バイオエタノール製造の最適条件の探究 ~廃棄野菜のアップサイクルを目指して~千葉県千葉市立都賀中学校 科学技術部 3年山本 佳音さん・加藤 咲菜さん・地引 明良さん・大谷 颯さん・野口 陽菜さん・中田 光さん・湯浅 那央さん・横田 大智さん -
 佳作カラタチのトゲのつき方にはどのような規則性があるか茨城県茗溪学園中学校科学部 生物班 3年道上 瑞涼さん・鳥山 櫂さん・田中 蒼一郎さん・小林 亮也さん・鬼澤 吏玖さん
佳作カラタチのトゲのつき方にはどのような規則性があるか茨城県茗溪学園中学校科学部 生物班 3年道上 瑞涼さん・鳥山 櫂さん・田中 蒼一郎さん・小林 亮也さん・鬼澤 吏玖さん -
 佳作ムクドリの飛び立ち距離と環境の関係神奈川県逗子開成中学校 3年加藤 匠さん
佳作ムクドリの飛び立ち距離と環境の関係神奈川県逗子開成中学校 3年加藤 匠さん -
 佳作ホタルの光学構造を模倣した高効率LED設計 ~生物発光に学ぶ都市光害削減技術~京都府京都市立西京高等学校附属中学校 1年サジド ムハンマド アマールさん
佳作ホタルの光学構造を模倣した高効率LED設計 ~生物発光に学ぶ都市光害削減技術~京都府京都市立西京高等学校附属中学校 1年サジド ムハンマド アマールさん -
 佳作車を1km走らせるには何個のペットボトルキャップが必要か茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校 8年武井 諒太さん
佳作車を1km走らせるには何個のペットボトルキャップが必要か茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校 8年武井 諒太さん -
 佳作カブトムシの生存競争 大きい方、小さい方どちらが有利? ~食べられやすさ、環境の違いから調べる~ 昆虫の研究 Part5茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校 7年岩本 紗和さん
佳作カブトムシの生存競争 大きい方、小さい方どちらが有利? ~食べられやすさ、環境の違いから調べる~ 昆虫の研究 Part5茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校 7年岩本 紗和さん -
 佳作漢方薬の原料を自宅で栽培してみよう!兵庫県須磨学園中学校 3年相川 彩恵さん
佳作漢方薬の原料を自宅で栽培してみよう!兵庫県須磨学園中学校 3年相川 彩恵さん -
 佳作2年間の観察で絶滅危惧種を見つけた!関東地方野鳥生息場所調査神奈川県川崎市立御幸中学校 3年鈴木 陽矢さん
佳作2年間の観察で絶滅危惧種を見つけた!関東地方野鳥生息場所調査神奈川県川崎市立御幸中学校 3年鈴木 陽矢さん -
 佳作幼虫のマット環境と成長について ~コクワガタの幼虫の飼育を通して~愛知県名古屋市立城山中学校 3年白木 壮さん
佳作幼虫のマット環境と成長について ~コクワガタの幼虫の飼育を通して~愛知県名古屋市立城山中学校 3年白木 壮さん -
 学校奨励賞愛知県西尾市立鶴城中学校
学校奨励賞愛知県西尾市立鶴城中学校 -
 指導奨励賞東京都東京学芸大学附属竹早中学校金子先生
指導奨励賞東京都東京学芸大学附属竹早中学校金子先生 -
 指導奨励賞大分県 理科教室加世田 国与士先生
指導奨励賞大分県 理科教室加世田 国与士先生 -
 指導奨励賞静岡県焼津市立大村中学校大塚 昌裕先生
指導奨励賞静岡県焼津市立大村中学校大塚 昌裕先生
文部科学大臣賞
恐竜の足跡の研究 ~僕の9年間の研究成果総括編~
静岡県藤枝市立高洲中学校 3年
小崎 惇さん
1等賞
マッチョ・シルク ~プロテインで育てたカイコ~
東京都東京学芸大学附属竹早中学校 3年
土屋 光伸さん
2等賞
分光色差計を使ったAGEスケールの開発 ~誰でも簡単にできる糖化反応の評価方法~
大分県立大分豊府中学校 2年
宮﨑 香帆さん
3等賞
アゲハ蝶類の蛹化成長曲線と開翅長との関連について
静岡県焼津市立大村中学校 1年
青木 聡さん
秋山仁特別賞
アリの嗅覚能力と孤立アリが抱えるストレスについて アリの研究パートⅢ
福井県福井大学教育学部附属義務教育学校 9年
八木 詩月さん
オリンパス特別賞
両利きになることを支援する装置の開発3
静岡県静岡大学教育学部附属静岡中学校 2年
辻󠄀 知里さん
継続研究奨励賞
遠州、東三河地域における二ホンアカガエルとヤマアカガエルの繁殖条件とすみ分け
静岡県浜松市立可美中学校 3年
伊藤 壮太さん
佳作
えっ?何で漏れないの!?
愛知県西尾市立鶴城中学校 タンクブロメリア班 3年・1年
グェン カンアンさん・山根 悠嗣さん・小林 蒼空さん・馬場 陽大さん・レ ファイ バオさん・馬場 崇帆さん
佳作
バイオエタノール製造の最適条件の探究 ~廃棄野菜のアップサイクルを目指して~
千葉県千葉市立都賀中学校 科学技術部 3年
山本 佳音さん・加藤 咲菜さん・地引 明良さん・大谷 颯さん・野口 陽菜さん・中田 光さん・湯浅 那央さん・横田 大智さん
佳作
カラタチのトゲのつき方にはどのような規則性があるか
茨城県茗溪学園中学校科学部 生物班 3年
道上 瑞涼さん・鳥山 櫂さん・田中 蒼一郎さん・小林 亮也さん・鬼澤 吏玖さん
佳作
ムクドリの飛び立ち距離と環境の関係
神奈川県逗子開成中学校 3年
加藤 匠さん
佳作
ホタルの光学構造を模倣した高効率LED設計 ~生物発光に学ぶ都市光害削減技術~
京都府京都市立西京高等学校附属中学校 1年
サジド ムハンマド アマールさん
佳作
車を1km走らせるには何個のペットボトルキャップが必要か
茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校 8年
武井 諒太さん
佳作
カブトムシの生存競争 大きい方、小さい方どちらが有利? ~食べられやすさ、環境の違いから調べる~ 昆虫の研究 Part5
茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校 7年
岩本 紗和さん
佳作
漢方薬の原料を自宅で栽培してみよう!
兵庫県須磨学園中学校 3年
相川 彩恵さん
佳作
2年間の観察で絶滅危惧種を見つけた!関東地方野鳥生息場所調査
神奈川県川崎市立御幸中学校 3年
鈴木 陽矢さん
佳作
幼虫のマット環境と成長について ~コクワガタの幼虫の飼育を通して~
愛知県名古屋市立城山中学校 3年
白木 壮さん
学校奨励賞
愛知県西尾市立鶴城中学校
指導奨励賞
東京都東京学芸大学附属竹早中学校
金子先生
指導奨励賞
大分県 理科教室
加世田 国与士先生
指導奨励賞
静岡県焼津市立大村中学校
大塚 昌裕先生
各年度のコンクールまとめや入賞作品
これまで入賞した作品を検索できます